4月10日(金)の給食メニュー


わかめごはん ・ しらたまだんごじる ・ わかどりのスタミナやき ・ しまなみジュレサラダ ・ おいわいこうはくゼリー
今日は、『口は「幸せ」のもと』という言葉についてお話します。口にはたくさんの幸せなことが集まっています。お友達とおしゃべりする、体の中で、こんなに幸せなことの集まっている場所はありません。そして入れる「食べもの」と、出す「言葉」の玄関でもあります。食べるものを選んで体と心を健康にするように、出ていく言葉も、まわりを幸せにできるものを選びたいですね。
4月9日(木)の給食メニュー


ごはん、糸こんにゃく卵とじ、揚げ出しごとうふ、しらすあえ、牛乳
新年度がスタートし、今日から給食も始まりました。久しぶりの給食ですが、新しい学年・教室・先生と食べる味はどうでしょうか? おぼんの上をじっくりと見てみましょう。量が少し増えているのに気がつきましたか。一つ学年が進み、体がどんどん大きくなっているため、丈夫な体でいるための栄養もたくさん必要になるからです。なるべく減らさないで、しっかり食べましょうね。今年は、学校中で完食を目指してほしいです。給食の感想や、リクエストなどありましたら、どんどん聞かせてください。待っています。
桜がとても美しく咲きほこっています。
今日は久しぶりに全校生徒が登校し、学校がとても明るくなりました。
新しい4人の先生方もお迎えしました。
8人の1年生を迎える入学式も盛大に行われました。
素晴らしい天候の下、令和2年度の吉海小学校が始まりました。



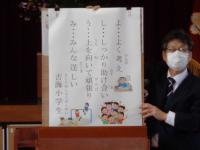



愛媛県内の新型コロナウイルス感染症拡大を受け、入学式準備と入学式を次のように変更させていただきます。
① 入学式準備について(5・6年生のみ)
5・6年生による入学式準備は中止し、教職員で準備します。そのため、5・6年生のみなさんはお休みとします。
② 入学式について
参加者の間隔を十分に取り、換気を行った上で実施します。なお、国歌「君が代」斉唱と在校生お祝いの言葉(校歌斉唱)は中止とします。
③ 春休み中の旅行について
子どもさんが春休み中に新型コロナウイルス感染症拡大警戒地域(首都圏、関西圏等)に旅行された場合は学校までお知らせください。
晴天に恵まれ、卒業証書授与式が行われました。
卒業証書を受け取った後、中学生になってがんばりたいことを一人一人、堂々と発表しました。
規模を縮小しての式でしたが、心のこもった思い出深い卒業式となりました。
6年生のみなさん、保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。






明日、24日(火)は、卒業式です。
今日は、教職員で卒業式の準備をしました。
卒業生の皆さん一人一人の笑顔を思い浮かべながら、最高の一日にするために、丁寧に掃除をしました。
準備は整いました。
明日、卒業生の皆さんを待っています。



久しぶりに、朝から元気のよい挨拶が、校庭に響きわたりました。学校に活気があふれます。
6年生は、卒業式のリハーサルを行いました。卒業を控え、表情も引き締まっています。
1年生から5年生は、各学級で、臨時休業中の様子を聞いたり、課題を確かめたりしていました。
これから、また一週間ほどの休みとなります。
規則正しい生活をして、体調に十分に気を付けましょう。



全校登校日に、休業中の学習の様子を聞くと、復習をしっかりとしているようです。
臨時休業中における学習支援のために、いろいろなコンテンツがあります。
それを紹介します。
① ラインズeライブラリ
予習、復習ができます。使用方法については、3月3日にプリントを配布しているので、そちらをご覧ください。
② 愛媛県教育委員会ホームページ
重要 新型コロナウィルス感染症関連情報をクリック → 臨時休業期間における学習支援コンテンツの紹介
このコンテンツの中から、文部科学省に開設された学習支援コンテンツポータルサイトへもアクセスできます。
ご家庭での学習にお役立てください。
3月16日(月)は、全校登校日です。
3月3日に決めた新しい登校班で、集団登校です。
帰りは、1年から5年までは集団下校となります。
6年生は、卒業に向けての準備がありますので、集団下校はしません。
体調が悪いときは無理をしないようにし、登校するときは、できるだけマスクを着用するようにお願いします。
みなさんに会えるのを楽しみにしています。
臨時休業に入り、一週間が過ぎました。
毎日、どうしているかな?元気かな?と、気になっていましたが、先日、家庭訪問で久しぶりにみんなの元気な様子を聞くことができ、安心しています。
学校では、卒業式に向けて少しずつ準備を進めています。
卒業生にとって大切な一日となるよう、準備を進めているので、みなさんも体調に十分に気を付けてください。


