1月13日(木)給食メニュー

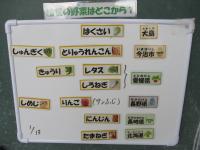
ごはん ・ 寄せ鍋 ・ れんこんのかき揚げ ・ りんごとすき昆布のサラダ ・ 牛乳
日本では、1000年以上も前から、イナゴなどの昆虫が食べられていたことが文献に残されています。また、太平洋戦争の終わりごろから戦後3年ごろまでの食糧難の時代には、日本全国でイナゴ類やハチ類の幼虫、カイコのさなぎなどが食べられていました。今も日本の一部の地域では食文化として根付いています。昆虫食は、今、世界的な人口増加による食料不足などの問題を解決するものとして注目されています。それは、養殖するときに温室効果ガスの排出量が少ないことや、エサが少なくて済むことなどが理由としてあげられています。昆虫は、その見た目から敬遠されることも多いのですが、今は粉末にして、いろいろな食品が作られるようになっています。気になった人は、調べてみてくださいね。
今日は様々な学年で書き初め大会が行われました。
1・2年生はフェルトペンでB5判用紙に、3年生以上は毛筆で書初用紙(半折)に、課題の文字を一生懸命書きました。
特に3年生以上は、普段とは異なる用紙に限られた枚数で文字を書くので、子どもたちの緊張した雰囲気がこちらにまで伝わってきました。
子どもたちの力作は、教室や階段に掲示されますので、機会がありましたらご覧になってください。



1月12日(水)給食メニュー


ごはん ・ 虎豆と鶏肉のトマト煮 ・ さばのアーモンド揚げ ・ 青じそドレッシングサラダ ・ 牛乳
今日は2のつく「ピースの日」です。今日の豆料理は「虎豆と鶏肉のトマト煮」です。虎豆は、加熱する前は虎の模様に似ているので、虎豆と言われています。特徴は、柔らかいので、煮えやすいことです。また、粘りもあり、おいしく食べられます。
また、今日は愛媛県が開発した「ひめの凛」という名前のお米を使っています。大粒で、しっかりとしたかみごたえとツヤがあるのが特徴です。いつもと違うご飯を味わっていただきましょう。

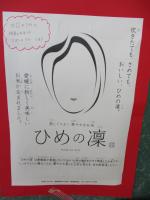
元気良く、きらきらとした表情で登校してきた子どもたち。
教職員一同、喜びを感じています。
児童は、校内放送で行われた始業式に、凛とした態度で参加しました。
代表児童の発表、校長先生や生徒指導主事の先生の話を聞きながら、気持ちが引き締まっているようにも感じました。
久しぶりに味わう給食には、笑みがこぼれていました。
今年も、幸多き1年になりますように。



1月11日(火)給食メニュー


セルフパン ・ ラビオリスープ ・ セルフドッグの具(ボイルウインナー、ボイルキャベツ) ・ ジャーマンポテト ・ 牛乳
あけましておめでとうございます。早いもので、1年のまとめの3学期が始まりました。寒い日が続きますが、教室の換気や手洗いをしっかり行い、給食では「黙食」を徹底するなど、感染予防にも努めましょうね。さて、みなさんは、給食で苦手な食べ物が出たらどうしていますか?全く手を付けずに、残している人もいるかもしれませんが、ひと口でいいので食べてみてください。初めは苦手でも、食べ慣れることで、だんだんとおいしく感じるようになっていきます。また、味覚は成長とともに変わっていくので、苦手だと思っていたものでも、食べて みたらおいしかったということもあります。今年は、「トラ年」、苦手な食べ物にもぜひ「トラい!」してみてくださいね!
今日の給食のセルフドッグは、子どもたちが自分で具材をはさめて、楽しく食べました。


今日は2学期の終業の日です。
保護者の皆様には何かとお世話になりました。
ありがとうございました。
さて、終業式では、児童代表2名が今学期がんばったことや3学期への抱負などを発表しました。
校長講話では、1学期から呼びかけている「チャンス・チャレンジ・チャンピオン」のめあてが達成できたか、その振り返りの時間がありました。
教室では、『あゆみ』をもらい、冬休みへの希望と期待を持って、元気に集団下校をしました。
短い冬休みですが、どうか安全で、有意義な日々をお過ごしください。



9月に始まった2学期ですが、あと1日(終業式)を残すだけになりました。
明日は、子どもたちが楽しみにしている「クリスマスイブ」です。多分、一人一人の頭の中には、様々な夢や想像が膨らんでいることでしょう。今日の子どもたちは、そういうものを感じる表情をしていました。
5時間目の3年生の音楽の授業では、木琴や鉄琴、トライアングル、鈴など、様々な楽器に分かれて、「雪のおどり」という曲を演奏しました。雪がしんしんと積もっていく様子や、子どもたちがわくわくしている様子が伝わる演奏でした。改めて、歌や曲、そして、子どもたちの持つ力を感じる時間となりました。
このような雰囲気で年末・年始を迎え、楽しく穏やかな冬休みを過ごしてほしいと願っています。



12月23日(木)給食メニュー


大根ピラフ ・ クラムチャウダー ・ クリスピーチキン ・ シーザーサラダ ・ ブッシュドノエル ・ 牛乳
今日は、一足はやいですが、クリスマス献立です。チャウダーは、魚介類、じゃがいも、ベーコンなどを入れた、アメリカ合衆国のスープです。アメリカは移民の国なので、イギリス移民の多かったボストンでは、生クリームを加えて白い色のクリームスープ味、イタリア移民の多かったマンハッタンでは、トマトを加えた赤い色のトマト味、といった具合に、味付けや加える具材が違います。日本では、白いクリームスープに仕上げたものが一般的です。クラムは、英語の「clam」で、二枚貝のことです。アメリカのチャウダーには、はまぐりに似たホンビノスガイを使うことが多いそうですが、日本では代わりとして、はまぐりやアサリを使います。クリスマス気分を味わって、いただきましょう。
1松、4松、5松では給食時間に、調理場内でクリスマス スペシャルメニューを作る様子をまとめた動画を視聴しました。


4年生
4年生は、音楽の時間に「まほうのチャチャチャ」という曲を学習しています。
今日は、5種類のリズム・パターンから一つを選び、曲に合わせて打楽器を打ちました。
上手に打てるようになったら、リズムを打ちながら歩き、同じリズムを打っている人同士で集まりました。
曲に合わせて打つだけでも難しいのですが、友達の打つ音をよく聞きながら仲間を探すことができました。


12月22日(水)給食メニュー


ごはん ・ かぼちゃのそぼろ煮 ・ 白身魚のねぎソースかけ ・ 柚子ドレッシングサラダ ・ さいぎり納豆 ・ 牛乳
今日は、冬至です。冬至とは、一年で昼が一番短く、夜が一番長い日のことです。英語で冬至は「winter solstice」といいます。「soltice」は「てっぺん」という意味です。古代ローマでは、太陽の力が弱くなるこの時期に、人々が集まって楽しく過ごしながら太陽のよみがえりを祝う冬至祭が広く行われました。これが、クリスマスの原型になったそうです。日本では、冬至にかぼちゃを食べますが、お隣の韓国では、小豆がゆを食べたり、「へび」の字を逆さにした魔よけ札を貼り出します。1年で一番昼の短い日、世界でも様々な行事があるのですね。
また、児童玄関には、「柚子」を飾っています。実物を見たことない児童も多くおり、休み時間には触ってみたり、匂ってみたりしている様子でした。ぜひ、今日は柚子湯につかってみてくださいね。
